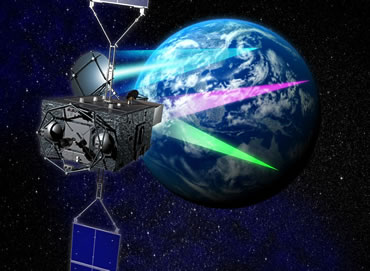先日、我が町の「少年教室 夏の裏磐梯を探検しよう」の引率ボランテイアに参加した。
町内2校の小学生、40名弱を大人4人がお世話した。父兄は同行せずに、子供の自立の勉強イベントだ。
子供達は校舎が今回の大震災で倒壊したので、それぞれ4校の大きな被害が無かった、別の学校へ友達と別れ分散して通学してる。放射能汚染の影響で、長袖を着て、外で遊べず、プールにも入れず、水筒を下げて、通学しており、かなりストレスが溜まっている様子だ。
中央公民館に朝、集合して、父兄が手を振り見送る姿を
後にして、観光バスは発車して、一路、裏磐梯五色沼に向かった。ペットボトルの水が配られた。好きな友達同士で席に座り、期待に胸を含ませる、笑い声が車内に広まっていた。

私の受け持ちは3,4年生の女の子8人グループだ。子供達がころんで、擦りむいた時ようの薬一式のビニール袋が引率者に配られた。五
色沼入口から約1時間の五色沼巡り散策が始まった。子供達に「五色沼は湖の色がそれぞれに色が変化し、綺麗だよ」と話した。「本当だ青色だ、緑色だと」キャーキャー騒いだ。「先生、走っても良い?」「道がデコボコで危ないから気おつけてね」「大丈夫だよ」と言いながら数名が先に走った。20年程前に、絵の仲間と沼の前でのスケッチ旅行、バーベキューを楽しんだことを思い出した。
咳が酷い3年生の子は走らずに、一緒にゆっくりと歩いた。「大丈夫、熱は無い?」おでこを触るが、熱は無い。「お母さんが胸に咳止めのテープを貼ってくれたよ」と言いながら、胸を見せてくれた。「お尻にも貼るともっと良いよ」「ヤーダー、嘘だ」と言いながら質問を沢山、浴びせてきた。「この草は何て言うの?」「この虫は?」「空気がカブトムシの甘い臭いがするね」「ここは放射能は大丈夫かな?」・・・。先に走った子供達が待っていてくれ、追いつくと、又、走っ

て行った。8人が必ず居るか、子供達同士で、その都度確認しながら、「チャント居るよ先生」と、嬉しそうに叫んでいた。
裏磐梯高原駅に先回りして、待っていたバスに乗り込む。直ぐ近くの裏磐梯ラビスパに着いて、楽しみなバイキング昼食だ。子供達は何回も好きな食べ物を取りに行った。私が蕎麦、オクラを食べていたら、
「このスパゲテイ辛い」「先生、お蕎麦と交換して」「私、オクラ大好き、先生、何処に有ったの?」「どうして好きなの?」「お爺さんが畑から採って来て、美味しいから」我が町は田園に囲まれた美しい町が放射能に汚染されてる。
さー。プールだ。この施設は子供から大人まで楽しめる、深さがいろいろ、流れるプール、螺旋トンネル落下ウオターシュート、温泉、サウナ、等が備わっていた。先ほどの咳の酷い子は何回もウオターシュートの高い階段を上って、落下滑って、時間一杯、楽しんでいた。不思議なことに、いつの間にか咳が出ていない。「先生、バスの席は私の隣に座って!」と、私の手を引っ張った。
プールで遊び過ぎて、予定より1時間程、遅れてバスは保原に向かった。途中、裏磐梯道の駅で休憩し、ソフトクリーム売店に並んだ。蕎麦ソフトには驚いた。咳の酷い子は私の手を放さず、一緒にソフトを食べた。中央公民館では、首を長くして、父兄が待っていた。先ほどの子は、おばあさんと一緒に私の車まで来て「さようなら」「今日はありがとう」「又、会おうね」と言って別れた。
中国10余年生活した時に、家族帯同赴任者の子供達の父兄からの強い要望で、南京の日系企業の協力で「南京日本語補習授業校」の設立に奔走し、いろいろと苦労したが、毎週、土曜日に市内の各マンション、ホテルで待つ子供達をバスに乗せ、郊外の補習授業校へ引率した。勉強をしたり、皆と遊んだりと、楽しかったことが、走馬灯のように、思い出された。
伊達市の霊山児童館に毎月、子供将棋の指導(遊び?)で楽しんでいるが、市内の小中学校のプール除染、校庭のグランド土削りが徐々に始まったが、子供達が安心して、屋外で飛び回れるように成るのは何時のことか?全て、私達、大人の責任だ。安全な環境の再現まで、出来ることから参画努力したい。
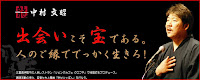
 中村文昭さんの講演会を友人と相乗りで車を走らせ、郡山ユラックス熱海で拝聴長した。会場には若者が半数近くの綺麗な浴衣を着た女性達も含め約300人弱の大盛況だった。
中村文昭さんの講演会を友人と相乗りで車を走らせ、郡山ユラックス熱海で拝聴長した。会場には若者が半数近くの綺麗な浴衣を着た女性達も含め約300人弱の大盛況だった。


 私の受け持ちは3,4年生の女の子8人グループだ。子供達がころんで、擦りむいた時ようの薬一式のビニール袋が引率者に配られた。五
私の受け持ちは3,4年生の女の子8人グループだ。子供達がころんで、擦りむいた時ようの薬一式のビニール袋が引率者に配られた。五
 「ドラッカー7つの教訓(前編)」
「ドラッカー7つの教訓(前編)」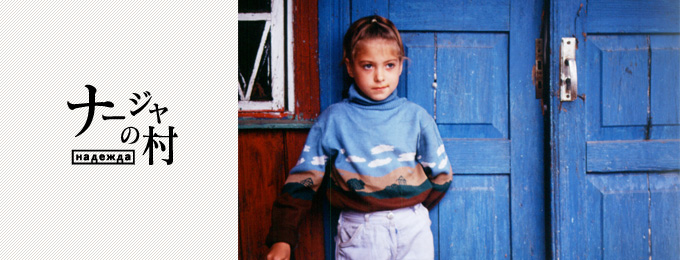
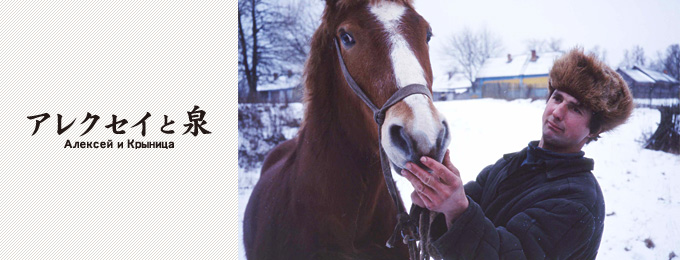

 「オイシックス」を起業しました。
「オイシックス」を起業しました。